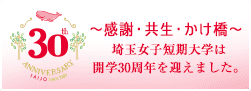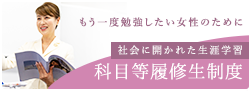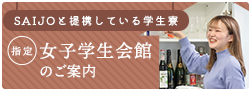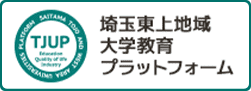医療事務に必要なスキルとは|取得しておきたい資格や学べる学校について
医療事務は、病院やクリニックなどの医療機関で受付や会計、医療費の計算などの様々な業務を行っています。
医療事務という職業は、進行していく高齢化社会においてさらに需要が高まることが予想され、景気の良し悪しの影響も受けにくく、目指す方も多いのではないでしょうか。
今回は、医療事務の仕事内容や働き方、目指すために習得しておきたいスキルや資格とそれらを学べる学校についてご紹介します。

医療事務の仕事内容
医療事務の仕事は、一般企業の事務職とは異なり、パソコンや書類に向かって黙々と事務作業を行うものではありません。
そこでまずは、多岐にわたる医療事務の仕事の内容を紹介します。
医療機関の顔となる「受付・会計業務」
医療事務の仕事で最も身近に感じるのは、「受付・会計業務」だと思います。
私たちが病院やクリニックにかかった際、まず最初にコミュニケーションを取るのが受付を行う医療事務のスタッフです。
患者さんから保険証を受け取り、診療室や処置室などへ案内し、診察券やカルテを作成します。
診療が終了後、診療費用を計算して会計を行い、処方箋などをお渡しします。
実際に患者さんに接するため、医院の顔となる業務と言えるでしょう。
医療事務の専門知識が求められる「レセプト業務」
「レセプト業務」は、医療事務の専門性が最も求められる業務です。
診療を受けた際にかかった費用は患者さんが全額負担しているわけではなく、その残りは保険証を発行している健康保険組合や国民健康保険組合から支払われます。
そのため医療機関側は、審査支払機関を通して健康保険組合や国民健康保険組合に診療費用の残りを請求しなければなりません。
この診療費用の請求の際に提出するのが、「レセプト(診療報酬明細書)」です。
このレセプトは、患者さんの氏名や傷病名、どんな処置を行いどんな薬を投与したのかといったカルテの情報をもとに、診療報酬点数を計算して作成します。
医療機関が得られる費用にかかわる業務であるため、専門的な知識や正確さが求められ、経営にもかかわる非常に大切な業務です。
医師や看護師をサポートする「クラーク業務」
「クラーク業務」は、比較的大きな病院で行われる業務で、主に「外来クラーク」と「病棟クラーク」に分けられます。
「外来クラーク」は、診察への誘導や検査の準備、問診票やカルテ・検査データの管理など、訪れた患者さんと医療スタッフの橋渡しする業務になります。
「病棟クラーク」は、入院にともなう事務業務のことであり、入院手続きや患者さんやご家族への対応・医師や看護師の指示する医療機器の準備・検査やリハビリに関する手配などが含まれます。
医療事務は、クラーク業務を通して、業務量が多く人手不足が問題となっている看護師や医師のサポートを行い、診療が円滑に行われるための大切な役割を担っています。

医療事務という職業を選択するメリット
都心・地方にとらわれず、どこでも必要とされる職業
医療事務の勤務先は、大きな病院だけではなく、地域に根付くクリニックや歯科医院、調剤薬局、検診センターなど様々です。
こういった医療機関は、都市部はもちろん、全国各地どこにでもあります。
そのため、医療事務の仕事も全国どこにいても需要のある職業であり、ライフステージの変化に伴い引越しが必要となった際でも、これまでの経験を活かして再就職しやすいのは大きなメリットと言えるでしょう。
雇用形態が様々
前項で述べたように、医療事務の勤務先が様々であることに加え、雇用形態も様々です。
安定した収入や充実した福利厚生を求める場合は正社員、子育てや介護等の時間も確保したい場合はパートやアルバイト、様々な医療機関で経験を積みたい場合は契約社員など、働き方を柔軟に検討することができます。
医療事務のスキルや経験を習得しておけば、一生の仕事としてライフスタイルが変化しても様々な場所で活躍することができるでしょう。
医療業界に携わるやりがい
医療事務は、実際に医療行為を行うことはできませんが、紛れもなく医療の現場を支える大切な職業です。
会計時に患者さんに「お大事に」と励まし「ありがとう」と感謝していただけるのは、人の役に立つ仕事をしている実感となります。
さらに、患者さんが元気になっていく姿を目の当たりにすると、大きな喜びややりがいを感じることができるでしょう。

医療事務に必要なスキルや資格
医療事務に向いている人
コミュニケーション能力のある人
医療事務は、患者さんはもちろん、院内の医療スタッフや医薬品や資材の販売業者など多くの人と関わらなければならないため、コミュニケーション能力が高い人は医療事務に向いています。
特に、常に忙しい医師や看護師とのチームワークを築くには、円滑なコミュニケーションを大切にしなければなりません。
マナー・ホスピタリティのある人
多くの患者さんは、体調が悪く大きな不安を抱えた状況で医療機関を訪れるため、医療事務には患者さんの気持ちに寄り添い不安を軽くできるような思いやりのある対応が求められます。
そのため、高いレベルのマナーやホスピタリティは身につけておかなければなりません。
PCスキルのある人
医療の現場は日々IT化が進んでおり、勤務先にもよりますが、電子カルテをはじめとしてほとんどの業務をデジタルで行うということもあります。
そういった環境にすぐに順応できるよう、これからの医療事務の業務においてパソコンのスキルは必要不可欠です。
数字に強い人
医療事務には、会計業務やレセプト業務など、数字を扱う業務がたくさんあるため、数字に強い人が医療事務に向いていると言えるでしょう。
数学は苦手……という人も多いかもしれませんが、高度な計算を求められるわけではありませんので、最低限の算数の計算を正確に行うことができれば問題ありません。
作業をスピーディに正しく行うことのできる人
高齢化社会の進んだ現在、医療の現場は日々多くの患者さんが訪れるため、業務量が膨大であり、いかに早く処理していくかが大切です。
また、患者さんの健康はもちろん、医院の金銭などに関わる業務も多いため、スピードだけでなく丁寧さと正確さも同時に求められます。
臨機応変な対応ができる人
医療の現場では、予期せぬ出来事が発生することもあるため、そんな時も臨機応変に冷静な対応ができなくてはなりません。
小さな子供や高齢の方、体の不自由な方も多いため、トラブルが発生したり困っている方がいたりした場合は、常に柔軟に対応できるようにしておくのが大切です。
勉強熱心で向上心がある人
医療事務の仕事は覚えるべきことが非常に多く、さらに医療業界は日々進化していて新しい技術がどんどん取り入れられます。
医療行為を行わないとは言え、知識として取り入れていかなければならないため、就職後も勉強をし続けることが必要となります。
取得しておきたい資格
医療事務になるために必須となる資格はありませんが、業務を行うにあたって必要となる専門知識を学ぶためにも習得しておきたい資格があります。
就職にも有利に働き、勤務先によっては収入面でも優遇されることが期待でき、就職後も知識として業務の役に立つ資格をご紹介します。
医療秘書技能検定
医療秘書技能検定試験とは、医療秘書教育全国協議会が認定する資格で、医療事務の専門知識と技能を認定する試験です。
現在、1級・準1級・2級・3級と4つのグレードがあり、レセプト業務に直結する医療報酬制度から、医学の基礎知識、医療に関する法制度、マナー・接遇に至るまで、医療事務として必要な知識が出題されます。
受験資格に経験や学歴などの制限はありませんが、高いグレードの級に合格するには独学では少し難易度が高い試験です。
医師事務作業補助技能検定試験
医師事務作業補助者とは、診断書等の書類作成やカルテ作成などの事務業務を医師に代わって行う仕事です。
この試験でも医療関連の法律や医療保障制度、医学や薬学の基本的な知識、診療報酬制度や電子カルテについてなどに関する筆記試験と、診断書や証明書などの医療療文書作成業務の実技試験があります。
診療報酬請求事務能力認定試験(日本医療保険事務協会)
診療報酬請求事務能力認定試験は、医療事務の要であるレセプト業務に必要なスキルを証明する資格であり、学科と実技の試験が設けられております。
医療事務関連で厚生労働省が認定している唯一の試験で、高い水準の知識とスキルが必要となり、合格率は30%ほどと大変難易度の高い試験です。
医事コンピュータ技能検定
医事コンピュータ技能検定は、日本医療事務協会が主催しており、1級・準1級・2級・3級と4つのグレードがあり、レセプト業務に関連する知識やコンピュータ関連の知識を問う筆記試験と、実際にレセプトを作成するという実技試験が行われます。
医療機関のIT化に伴い、コンピュータに関する技能は医療機関においても必須となるスキルですので、ぜひとも高いグレードの級まで取得しておきたい資格です。
電子カルテ実技技能検定
電子カルテ実技技能検定は、診察時の医師と患者のやりとりをシミュレーション化した問答形式問題を基に、電子カルテシステム(診療所、病院外来用)を操作し、電子カルテの操作方法を習得する検定です。
電子カルテシステムを実際に操作し、データを正しく入力できるかといった実技試験のみで構成されています。
まだまだマイナーな試験ではありますが、大規模な病院では一般的となった電子カルテを正しく使いこなして業務効率化に貢献できるスキルと言えるでしょう。
秘書検定
秘書検定とは、社会で働く上で誰でも身につけておきたい一般常識や敬語、電話応対、ビジネス文書などの知識を問う試験です。
医療事務の専門知識というわけではありませんが、患者さんやそのご家族、院内の医療スタッフ、外部の関係業者など、多くの方々とコミュニケーションをとるのに必要なマナーを学ぶことができます。

医療事務になるには
医療事務になるための学校
医療事務を目指すにあたり、前述のとおり必須となる国家資格や学歴の制限はありません。
しかし、医学や医療に関する法律・制度といった専門知識を要する業務もありますので、それらを習得しておくには独学だけでは挫折しやすいのも事実です。
医療事務になるための学校は、大学、短大、専門学校、通学講座、通信講座といった5種類に分類されます。
じっくり学びたい方は医療系や福祉系の4年制の大学への進学もおすすめですが、年間100万円ほどの学費が4年間かかってしまうことになるため、費用面で負担が大きいかもしれません。
その点、短大や専門学校は、2年間で効率よく医療事務に必要なスキルを学ぶことができるため、より早く社会に出て活躍したい方にはおすすめです。
医療事務を目指すなら、埼玉女子短期大学へ
埼玉女子短期大学では、医療事務として活躍していくためのスキルや知識を身につけることができ、資格の取得や就職まで充実したサポートを行なっております。
【埼玉女子短期大学をお勧めする理由】
- 取得しておきたい資格を、計画的に習得できるカリキュラムがある!
- 今後の医療機関では欠かせない、デジタル化に対応した講義を受講できる!
- 医療事務の仕事をする上で大切にしたい、マナー・ホスピタリティが身につく!
- 在学中に大学病院や総合病院での病院見学やインターンシップが体験でき、現場目線で実践的な学びがある!
- 医療事務としての経験豊富な教員による手厚い指導とサポートにより、高い就職率を実現!
- 同じく医療事務をめざす仲間に囲まれることで、モチベーションを維持できる!
まとめ
医療事務の仕事は、医療関係の専門知識に加え、デジタル化や今後の医療業界の発展、法改正などに対応していくことが必要となり、就職後後も向上心を持ってスキルや知識をを磨いていかなければなりません。
また、患者さんに接する機会も多いことから接客業の側面も併せ持ち、マナーやホスピタリティ、臨機応変に対応できる判断力やコミュニケーション能力も必要となります。
しかしその分、この先の高齢化社会ではますます需要が高まり、景気の変動にも影響を受けにくく、ライフスタイルが変わっても活躍し続けられる職業です。
医療事務を目指すには、必須の資格や学歴の制限はありませんが、しっかり知識とスキルを身につけるには、大学、短大、専門学校等への進学をお勧めします。
その中でも、埼玉女子短期大学なら、医療事務に必要なスキルや資格を身につけることができ、計画的に資格取得を目指せるカリキュラムをご用意しています。
より実践的な学びと就職活動のサポートも充実しており、高い就職率を誇っております。
医療事務として活躍していきたい方は、埼玉女子短期大学をぜひご検討ください。